ショート動画の人気とその理由
近年、TikTokやYouTube Shorts、Instagram Reelsなどのショート動画が大人気です。なぜここまで浸透したのでしょうか?
理由は「短時間で満足感を得られる」こと。
現代人は時間の使い方にシビアで、隙間時間にサクッと楽しめるコンテンツを求めています。
心理学で見る「せっかち」になるメカニズム
心理学的に、人は“待つこと”がストレスになりやすい生き物です。
ショート動画は脳に即時報酬を与えるため、「短い時間で結果を得る」体験が繰り返されることで、待てない脳の習慣が形成されやすくなります。
本記事では、手軽に短時間で「面白い」体験を視覚的に得ることができる時代になった弊害として人はせっかちになっているのではないか?という問いに関して心理的に解説していきます。
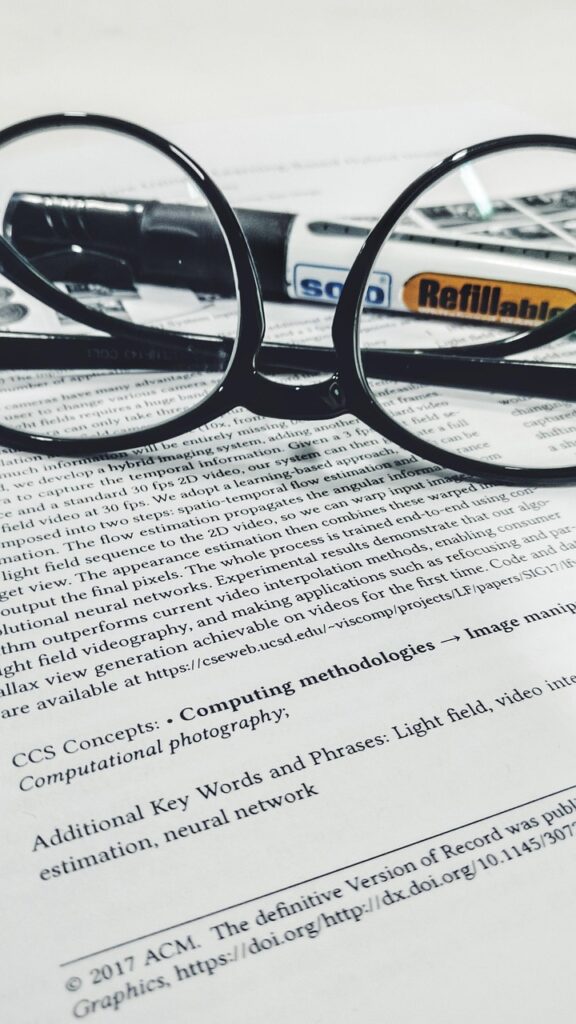
脳が求める「即時報酬」とドーパミンの関係
脳科学では、ドーパミンという神経伝達物質が「報酬系」を刺激すると快感を得られることが分かっています。ショート動画は短時間でドーパミンを繰り返し分泌させるため
長い動画や本を読むときに「退屈」を感じやすくなり、長い待ち時間を「損」であると感じやすくなっていきます。
このことから短期的報酬(ショート動画の視聴)を繰り返し得るとせっかちさが増すことが分かります。
ショート動画の流行が及ぼす文化的影響

ショート動画の流行は、
なぜ、
ショート動画が作った「切り抜き文化」
TikTokやYouTube Shortsのアルゴリズムは、
この影響で、
“作品全体を観なくても物語を知れる文化”が生まれました。
予告編よりも短い「ハイライト消費」
従来の予告編は数分でしたが、
倍速視聴が当たり前になった理由
時間を節約したい心理
NetflixやAmazon Prime Videoで導入された倍速再生機能は、
「
脳が求める“刺激の最適化”
脳が求める「即時報酬」とドーパミンの関係の部分でもお話した通りショート動画で刺激を短時間に得る習慣がつくと、
その結果、
制作者も変わり始めた映像コンテンツ
映画やドラマの冒頭数秒で視聴者を引き込む編集、
さらにはSNSでシェアされやすいショートフォーマットの制作が
「長編作品」から「切り抜き前提の作品」
現代人は集中力が低下している?
カナダのマイクロソフトの研究では、平均的な集中力の持続時間は2000年には12秒でしたが、2015年には8秒にまで短縮されたと言われています。
これはショート動画だけでなく、スマホ文化全体の影響ですが、短いコンテンツの増加はこの傾向を加速させていると考えられます。
スマホの流行だけではない!?せっかちになる社会的背景

認知負荷と注意の断片化
現代は情報量が多く、脳は効率的に処理しようと「
その結果、「一つのことに集中し続ける」能力が弱まり、
例:ショート動画で1本15秒 → 脳は「長尺=退屈」という認識に変化。
マルチタスク文化 → じっくり待つことがストレスになる。
社会・文化的要因
・テクノロジーの影響
オンラインショッピング → 翌日届くのが当たり前。
オンデマンド動画 → 待たずに観れる。
こうした「待たなくても手に入る」体験が待機行動を不快にする。
・競争社会の圧力
「時間=資源」「効率=善」という価値観が、待つ=
4. ストレスとコルチゾール
ストレス状態ではコルチゾールが分泌され、即決・即行動を促す(
慢性的ストレス社会では、全体的に待てない傾向が増す。
せっかちになるプロセスまとめ
-
短期報酬に慣れる(SNSや即レス文化)
-
長期報酬への忍耐が低下
-
待つこと=ストレスという脳の認識
-
社会的価値観がそれを強化
せっかちを防ぐためにできること
- 意識的に長い動画や本を読む時間を確保する
- 通知をオフにしてスマホを見る時間を減らす
- 「待つ」習慣をあえて作る(例:コーヒーをドリップで淹れる)
テクノロジーの進化は便利ですが、その影響を理解してバランスを取ることが大切です。



コメント